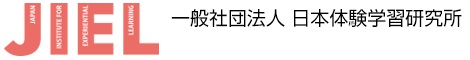柘榴
昔、一本の柘榴の木が庭にありました。
柘榴は毎年真っ赤な実を熟し、割れるとちりばめられた小さな顆粒が現れます。なにも手を加えないのにどの年も同じようにその表情を見せてくれました。
近くに中学校があります。疑うのもいけないのですが、おそらくは中学生がもいでいったのでしょう、その影響があったのかもしれません、いつしか柘榴は痩せ、枯れたのかどうか、知らないうちに木そのものを見なくなってしまいました。いつもあった真っ赤な色が、この季節になり、見られないとなると、その存在の重さ、大切さがひとしお感じられます。
近所のお宅に立派な柘榴があります。その木も毎年たわわに実をつけます。ひとつもいで食べてみたいな、といつも思っていました。ところがこの夏、驚愕したことにその木が伐採されてしまったのです。実が落ち、道路を汚してしまうと思ったからなのか、庭の手入れもままならないと高齢のご主人が思ったのか、私の風物詩の一ページに赤い衝撃が走りました。
鱗介(りんかい)の族は水を虚と為し、水の実(じつ)たるを知らず(佐藤一斎、言志後録53条)
(魚や貝などは水はないものと思い、水があってもそれに気づかない)
当たり前にあるものは、失って初めてその存在の大切さや影響の深さ、ありがたさまでも感じられることがあります。日常で日常を暮らしていると、ただ暮らすことに心を奪われ、生きることに心が向いていないのを感じるときがあります。
日々変わらないなかに変わるものがある。変わることへの鋭敏さと繊細さを研ぎたいと思います。