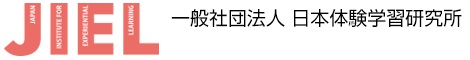自己をならうというは
歳をとったなあ、と思わせることにこの歳になるとたびたび出くわします。
飲んでいたとき、骨付きのでかい肉の塊が出てきました。「はじめ人間ギャートルズだ!」といったら、「なんですか、それ?」といわれた。えっ!ギャートルズ、知らないの?テレビ、家になかったんじゃない?とうそぶく。
学生のころ住んでいた街を何十年ぶりかに歩く。通っていた銭湯や大衆食堂は今はなく、えっ!まだあったの?と古い下宿先の2階の窓にかかったカーテンを見上げる。
新聞を開く。死亡欄や会葬のお礼の文字に目がいく。
ちょっと痛いところやぷっくりふくらんだところに気づいて、えっ!ガン?腫瘍?
最初にトマトとか野菜から食べ始めたほうがいい、とか話がいつの間にか健康や病気の話になっている。
勤めていた会社で同期だったヤツの喪中はがき。これは泣けた。なぜか泣けた。
髪の毛や、皮膚のシミやしわや、肉体の変化はそれを取り繕おうとしても真実を覆い隠すことはできず。あれやそれということばが増え、この人の名前なんだったかな?と目の前にいる人がだれだったかわからなくなったりする。
道元禅師はいいました。
自己をはこびて万法を修證するを迷とす、万法すすみて自己を修證するはさとりなり。
(いろんなことを考えているこの小さな自己をもっていって、万法の中で価値判断をするというようなことは迷いだ。自分の小さな考えをもっていて、ああでもない、こうでもないと、いろんなことを批判しながら生きていかなければならないような生き方が迷いだ。そうでなくて、外の姿に催されて、万法が自分を運んだくれるのだ-余語翠巖(1990)「自己をならうというは」地湧社)
余語翠巖さんがいうには、自分というものがあったり、仏道というものがあったり、迷いというものがあったり、悟りというものがあったりというように、二つずつ並べてどっちがどっちという世界ではない。二つあれば、それが迷いだ。二つあるから迷うのだ。一つなら迷いはない。
人も、物も、すべてが移り、変わっていく、来し方行く末の時間軸の中で、まるごとの存在がある。
あるテレビ番組で残ったことばがあります。
「運命ではない。運命にするのよ」